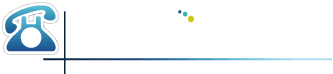一日の終わりに緊張や不安を抱えたまま布団に入ると、眠りが浅くなり、翌日の集中力や気分にも影響します。大切なのは「寝る直前だけ整える」のではなく、夜の時間全体をゆるやかに減速させること。本記事では、今日からできる具体的なリラックス手順をまとめました。
1. 夜をゆるやかに整える「90-60-30-10 ルーティン」

- 就寝90分前:重い食事・カフェイン・激しい運動をストップ。照明を少し落として準備を始めます。
- 就寝60分前:ぬるめの入浴(38〜40℃で10〜15分)または足湯。体温をいったん上げて下がるタイミングで眠気が来やすくなります。
- 就寝30分前:スマホ・PCはオフ。代わりに読書や軽いストレッチ、日記などの“静かな行動”へ。
- 就寝10分前:呼吸法+軽い伸ばしで心身を最終リセット。
2. 体の緊張をほどくナイトストレッチ(各20〜30秒)

- 首・肩:右手で頭を右へ倒し、左肩は下げる。反対側も。肩を前後にゆっくり大きく回す。
- 背中:椅子に座って両手を前で組み、背中を丸めて腕を前へ押し出す。肩甲骨の間を開くイメージで。
- 腰・脚:片脚を前に伸ばし、つま先を手前に引く。太もも裏の心地よい伸びで止める。
痛みが出るほど伸ばさず、「気持ちいい範囲」で止めるのがコツです。
3. 自律神経を整える呼吸(4-6 ブリージング)

- 背筋を立て、肩の力を抜く。
- 鼻から4秒かけて吸う。
- 口から6秒かけて細く長く吐く。
- これを5セット。慣れたら 4-7-8 なども可。
「吐く息を長く」を意識すると、副交感神経が優位になりやすくなります。
4. 頭の中を軽くする“3行ジャーナル”
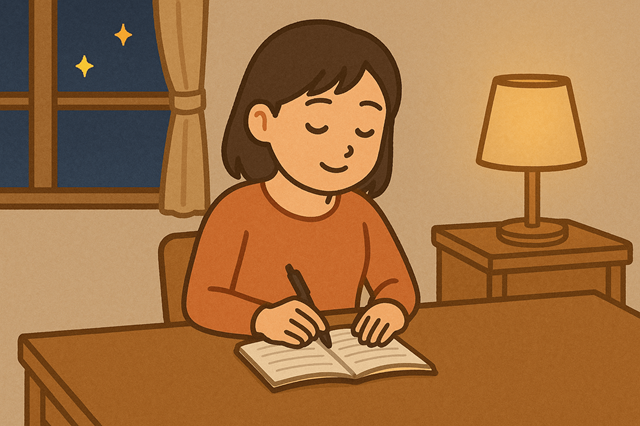
考えがぐるぐるすると眠りに入りづらくなります。ノートに事実だけを短く書き出し、思考を外に出しましょう。
- 今日の事実1行:(例)「A様の対応、明日に資料送付」
- 明日の一手1行:「10:00にテンプレ&追記事項で送信」
- 感謝・よかったこと1行:「同僚が引き継ぎを手伝ってくれた」
主観や反省は最小限でOK。「次にやること」を言語化すると、脳は安心して休みやすくなります。
5. 光・音・温度を“眠りモード”に

- 照明:寝室は暖色系・間接照明へ。ブルーライトの強い白色光は避ける。
- 温度・湿度:室温 18〜22℃、湿度 40〜60% を目安に。体感で微調整を。
- 音:静かな環境が基本。気になる場合は小さな環境音(雨音・ホワイトノイズ)を。
- 香り:好みが合えばラベンダー等のやさしい香りを少量。
6. 食べ物・飲み物のポイント

- カフェイン:コーヒー・エナジードリンク等は就寝6〜8時間前までに。
- アルコール:寝つきは良く感じても睡眠は浅くなりがち。量は控えめに。
- 温かいノンカフェイン:白湯・ハーブティー・麦茶などで“ほっとする感覚”を。
7. どうしても引きずる夜の「3分レスキュー」
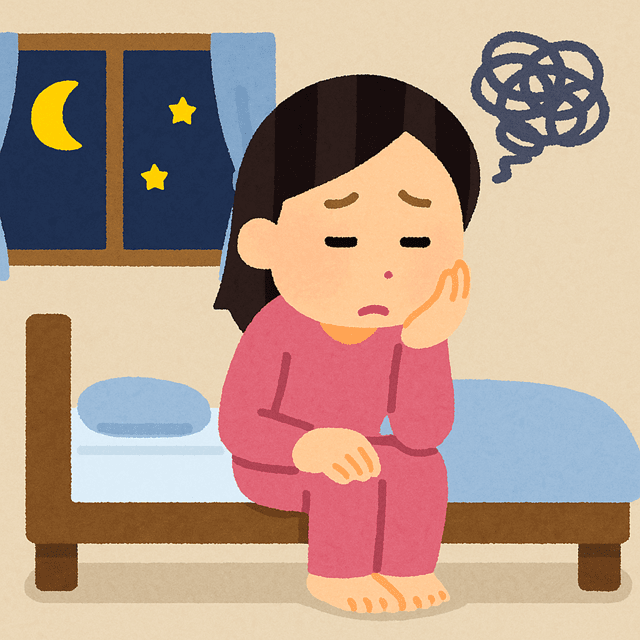
- グラウンディング5-4-3-2-1:見える5つ・触れる4つ・聞こえる3つ・嗅ぐ2つ・味わう1つを静かに数える。
- 筋弛緩法:手→腕→肩の順に10秒力を入れて、ストンと脱力。2〜3セット。
- 冷水リセット:手首を流水で20秒。余韻で深呼吸。
8. 眠れないときは「いったんベッドを離れる」

20分以上眠れないときは、いったん起きて薄暗い場所で単調な行動(軽い読書・呼吸法・ノート)に切り替えます。ベッドで時計を見続けるほど、脳は「ここは眠れない場所」と学習しがちです。
まとめ
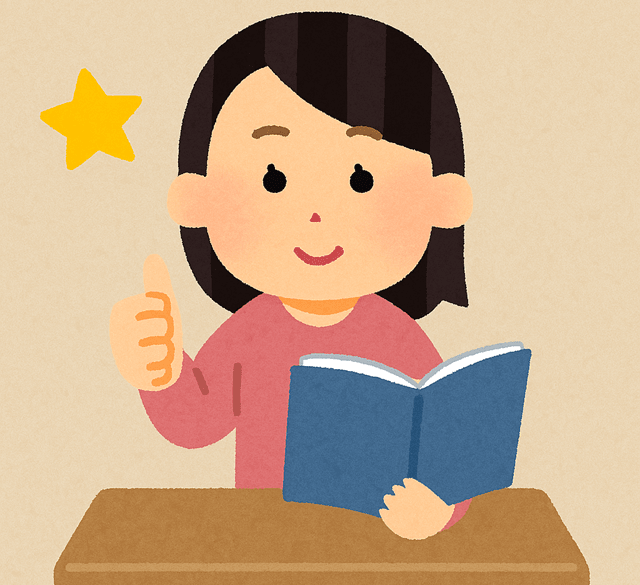
夜の時間をゆるやかに減速させるだけで、ストレスは翌日に持ち越されにくくなります。「90-60-30-10ルーティン」→ストレッチ→呼吸→3行ジャーナルの流れを基本に、光・温度・飲み物を整えましょう。完璧を目指すより、毎日7割で続けることが最大のコツです。体調に不安がある場合は、無理をせず医療・専門機関にご相談ください。