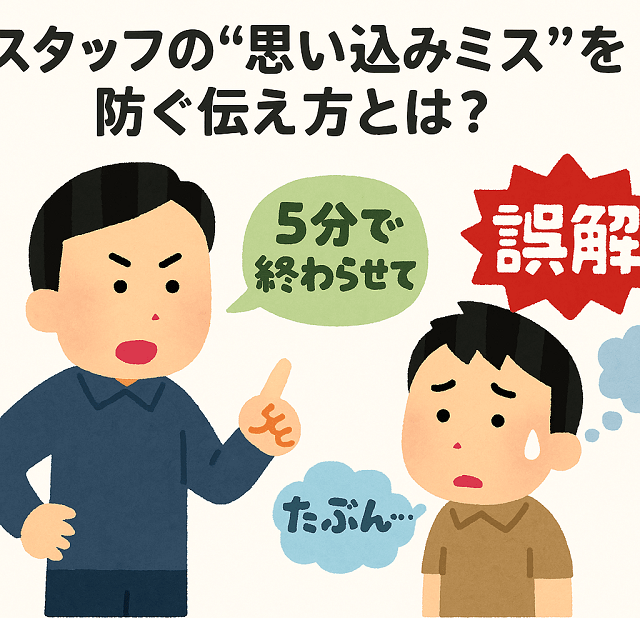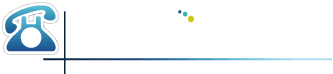現場でよくあるのが、「そうだと思っていました」「てっきりそういう意味だと…」という“思い込みミス”。指示した側は伝えたつもりでも、受け取った側が異なる解釈をしてしまうと、業務に支障が出てしまいます。
こうしたミスは、スタッフの能力というより「伝え方」に原因があることも多いもの。ここでは、スタッフ間の連携ミスを防ぐ伝え方の工夫をご紹介します。
1. 「抽象的な表現」は具体例を添えて

たとえば「ちゃんとしておいて」「いい感じにまとめておいて」などの曖昧な表現は、人によって受け取り方が異なります。「5分以内に終わるように」「○○のフォーマットに沿って」など、具体的な基準や例を添えることで、認識のズレを防げます。
2. 大事な指示は「復唱」してもらう

急ぎのときこそ、大切な指示ほど「伝えたつもり」で終わってしまいがちです。そんなときは「今の内容、復唱してもらってもいい?」と一言添えるだけで、お互いの理解度を確認できます。復唱は、ミスの予防だけでなく「聞く側の集中力」も高めてくれます。
3. 伝えた内容は「記録に残す」

口頭だけでのやりとりは、記憶違いや聞き漏れが起こりやすいもの。LINEやメモ、業務用チャットなどに簡潔に記録を残しておけば、あとで「言った・言わない」のトラブルも防げます。伝達漏れの防止にもなります。
まとめ:「伝えた」ではなく「伝わったか」が重要
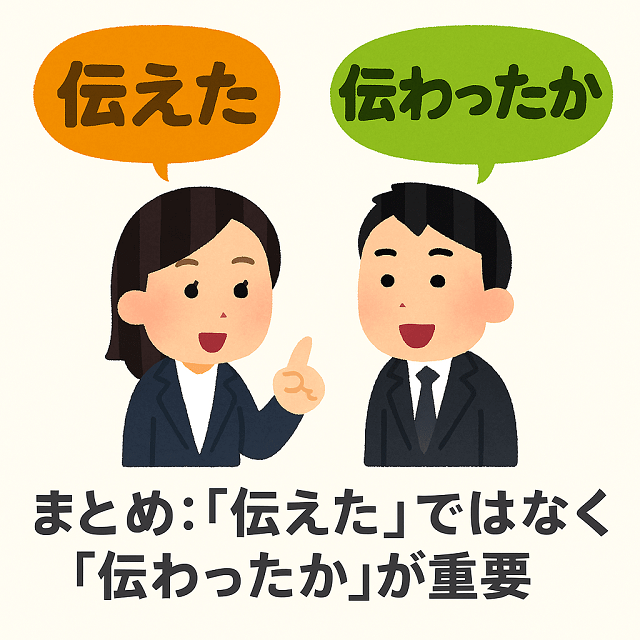
現場での連携ミスは、「能力」より「伝え方」が原因であることも多いです。「伝えた」で終わらせず、「伝わったか」を確認する習慣が、チームのミスをぐっと減らします。小さな工夫が、信頼される職場づくりにつながります。